私たちは、その旅が最後になるとは知らなかった。
交際して3年、何度も喧嘩をして、何度も仲直りをしてきた。
けれど、心のどこかで“もう以前のようには戻れない”という予感がしていた。
だからこそ、私は思ったのだ。
「一度、海の上でリセットしよう。自然の中で、二人で静かに過ごしたい」と。
彼も少し迷った顔をしながら「いいね」と答えた。
そうして選んだのが、北欧フィヨルドを巡るクルーズだった。
港を離れるとき、夕焼けが水面に溶けていた。
彼はカメラを構え、私は風に髪を揺らして笑った。
「やっと休めるね」
その言葉に、ほんの少し安堵が滲んでいた。
最初の数日は穏やかだった。
デッキでコーヒーを飲みながら氷河の景色を眺め、
夜はショーを見て、カクテルを飲み、
そのたびに少しだけ昔の二人に戻れた気がした。
だが、三日目の夜。天気が急変した。
空は鉛のように暗く、海は荒れ狂い、船は大きく揺れた。
窓の外には黒い波が何層にも重なり、
風の唸り声が船体を打ちつけた。
「大丈夫かな」
私が言うと、彼は「大丈夫。すぐ止むよ」と答えた。
けれど、その声にはどこか力がなかった。
揺れる船室の中で、私たちは小さなことで言い争いを始めた。
「どうしてそんな言い方しかできないの?」
「君だって、いつも自分の考えばかり押し通すじゃないか」
嵐の音と怒鳴り声が交錯した。
沈黙のあと、彼が小さく呟いた。
「このまま、何も言わずに終わるほうが楽なのかもね」
その言葉に、胸の奥がズキリと痛んだ。
私は何かを言い返そうとしたが、涙が先に溢れた。
翌朝、嵐は嘘のように静まっていた。
厚い雲の切れ間から、やわらかな光が差していた。
デッキに出ると、水平線の向こうに虹がかかっていた。
その美しさに言葉を失った。
隣に立つ彼も、しばらく黙ったまま虹を見ていた。
「きれいだね」
その一言に、すべての感情が詰まっている気がした。
私は笑おうとしたけれど、頬を伝う涙は止まらなかった。
その後の寄港地では、互いに無理に明るく振る舞った。
観光地で写真を撮り、
お土産を選び、
それなりに会話をした。
でも、心の中ではもう、何かが終わっていた。
沈黙が増え、笑いが減り、
それでも“旅の思い出を壊したくない”という気持ちだけが二人をつなぎ止めていた。
最終日、夜のレストランで最後のディナーをとった。
キャンドルの光が揺れる中、
彼はワインを口に運び、静かに言った。
「君といる時間は、嘘じゃなかったよ」
私は頷くしかなかった。
“ありがとう”と口に出すと、彼は穏やかに笑った。
その笑顔が、かえって切なかった。
下船の朝、港に着くと、空はどこまでも青かった。
タラップを降りる前に振り返ると、
彼がまだデッキに立っていた。
風に髪が揺れ、その姿がゆっくり遠ざかっていった。
私は手を振れず、ただ見つめることしかできなかった。
背中に感じる潮風が、まるで別れの挨拶のようだった。
帰国してしばらく経ったある日、
クルーズ中に撮った写真を整理していた。
その中に、嵐の翌朝に撮った一枚があった。
濡れたデッキ、遠くにかかる虹、そして彼の横顔。
その写真を見た瞬間、涙が溢れた。
悲しみではなく、不思議な静けさがあった。
「終わりって、こんなにも静かなんだ」と思った。
あの航海で私たちは、愛を失ったのではなく、
“過去を優しく手放す方法”を学んだのかもしれない。
今でも海の音を聞くたび、あの夜の風の匂いを思い出す。
そして心の中でそっと呟く。
――さようなら。あの旅に、ありがとう。

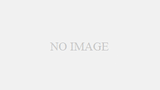
コメント