「ちょっと贅沢してみたい」——そんな軽い勢いで東南アジア周遊クルーズを予約した。私は35歳、独身。仕事は好きだけど、毎日終電と早朝ミーティングに挟まれて、気づけば季節が変わっている。友人と予定も合わず、「一人でも行けばいいじゃない」と背中を押したのは、思いのほか静かな自分の本音だった。
出航の日、港に立つと客船はビルのように大きくて、私の小さな迷いをあっさり飲み込んだ。チェックインを済ませ、海側キャビンのカーテンを開けると、視界いっぱいの水面がきらんと跳ねる。荷解きもそこそこにデッキへ出ると、潮の匂いと汽笛。胸のどこかがほどけた。
二日目の朝、寄港地ツアーの集合ラウンジ。緊張で少し早く着いてしまい、カメラの設定をいじっていると、隣の席から声がした。「そのレンズ、いいですね。旅にちょうどよさそう」顔を上げると、黒のキャップに日焼けした頬の男性。聞けば彼も一人旅で、写真が好きだという。「よかったら、今日のツアーご一緒しても?」彼の言葉に、自然と「お願いします」と答えていた。
市場では香辛料の匂いが渦を巻き、港では熱い風がスカーフを揺らした。彼は撮影スポットを見つけるのが早く、私の背後に広がるカラフルな家並みや、光の角度をさっと読んでくれる。「少し顎を上げて。そう、海を入れよう」シャッター音の合間に交わす短い指示が不思議と心地いい。カメラの背面に映った自分は、いつもより少しだけ解放的な顔をしていた。
船に戻ると、夕暮れのプールサイドで約束もしていないのにまた会った。「運命ですね」と冗談めかして言うと、「たぶん同じ時間に同じものを見たかっただけですよ」と彼は笑う。ディナーを予約していなかった私に、「相席、いいですか」。白いテーブルクロス、静かなグラスの音、窓の外を流れる暗い海。仕事の話、旅の失敗談、好きな音楽。話題はどこへ投げても弾み、気づけば前菜の記憶が薄れるほど笑っていた。
「明日の寄港、早起きして灯台に行きませんか。朝日がきれいらしい」夜風に髪をほどかれながら彼が言う。翌朝、まだ人の少ないデッキでコーヒーをすすり、薄紫の空に滲むオレンジを見た。波が光を砕き、船体が低く唸る。言葉は少ないのに、何か大切なものが静かに共有されている気がした。
旅は不思議だ。同じ船にいるだけで、生活のリズムが自然に重なる。昼は港町を歩き、夕方は写真を選び、夜はシアターでショーを見て、甲板で星を数える。私は自分の笑い声がこんなに軽かったかを思い出し、彼は「君はピントを合わせるのが上手い」と言ってくれた。「被写体がいいから」と返すと、「いや、視線がやさしいからだよ」と小声で言う。心臓が不意に跳ねた。
最終日前夜、デッキで風に当たりながら、彼がふっと真面目な顔になった。「クルーズが終わっても、会えるかな」「うん」自分でも驚くほど迷いがなかった。「じゃあ、次はどこの港で会う?」地図アプリの上で指が交差し、笑いが重なる。別れ際、彼が送ってくれた写真のフォルダ名は〈SAME HORIZON〉。同じ水平線、か。
帰国後、メッセージは日常の隙間を縫うように行き来した。近場の港へ日帰りの小さな旅にも出た。私たちはまだ恋人と呼ぶには慎重で、友人と呼ぶには温度が高い。その曖昧さが、海の上で揺れる月明かりみたいに心地よかった。
一人で乗り込んだはずの船で、私は“私のまま”でいられる誰かに出会った。クルーズは、ただの観光でも現実逃避でもない。日常と非日常のあわいに浮かぶ、誠実な偶然の装置だ。次の休み、私はまた予約サイトを開く。今度の航路は…どこへ向かおう。

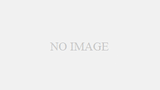
コメント